平昌オリンピックが無事に閉幕し、パラリンピックが開会されました。
前評判の芳しくなかった平昌五輪ですが、日本人のメダルラッシュも
あってか大盛況のうちに幕を閉じました。
しかし、五輪憲章は本来国同士の競争を否定しているので、あまり
「日本が日本が」と盛り上がるのはどうなのかな、という気もします。
真の五輪精神は、平和を尊ぶ仏教のこころに通じるものだといえるのかもしれません。
さて、上の文にも使っていますが、オリンピックのことを「五輪」と省略します。
これはなぜでしょう? オリンピックが五つの輪をシンボルマークにしているから、
というのはもちろん正解ですが、それだけだと答えの一部分。
じつはオリンピックを「五輪」と表現するのは、幻になった1936東京オリンピックの
報道のために、新聞記者がつかいはじめたものでした。
新聞の見出しは文字数が限られるので、当時そこに「オリムピツク」と6文字分も
使ってしまうのは悩みのタネだったそう。
なにかいい案はないか…と考えていた記者の方がひらめいたのが「五輪」だった
のだそうです。 「オリン」と「ゴリン」で発音も近いし、シンボルマークにも
ぴったりでとてもわかりやすい、ということであっという間に広まったそうです。
この発案者の方は、宮本武蔵の『五輪書』についてかかれた文章を読んでいるときに
ピンときたのだとか。
『五輪書』というのは、宮本武蔵が剣術の奥義を書き留めた武術の聖典のような
もので、タイトルになっている「五輪」とは、密教でこの世界のあらゆるものの基本、
いわば元素のようなものだと教えている「地、水、火、風、空」の5つの要素のことを
指します。
「五大」ともいいますが、五輪について考えることは、「この世界は何によって
できているのか」すなわち「世界とはなにか」を考えるに等しい壮大な問いとなります。
なかなか難解になりますが…つまり何がいいたいかというと、「五輪」ということばの
もとをたどると、仏教用語にいきつくということ。
仏教と「五輪」のあいだには浅からぬ御縁があるようです、というお話でした。
やはり、オリンピック精神は仏教のこころにつながっているのかも。
平昌パラリンピックでは日本のみならず、全ての選手にベストプレーで頑張ってほしいですね。
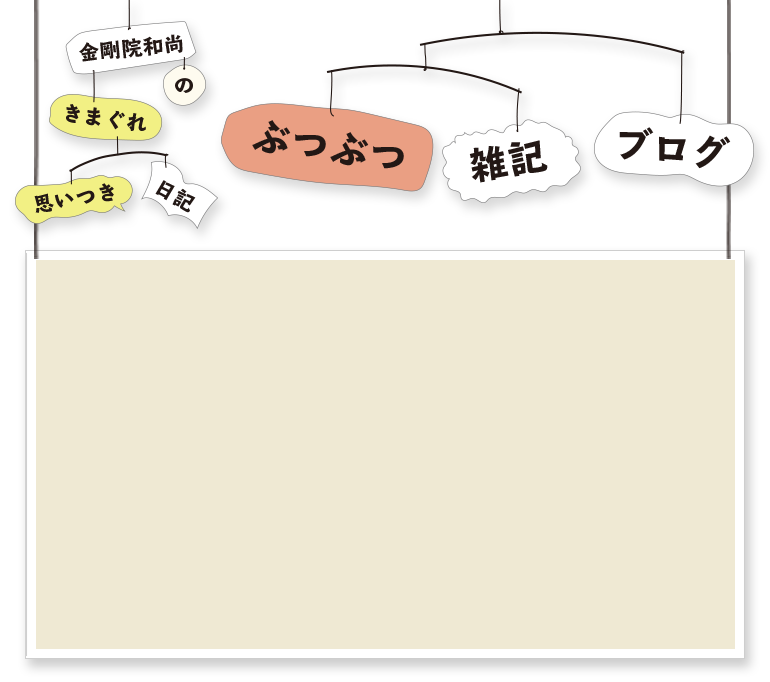
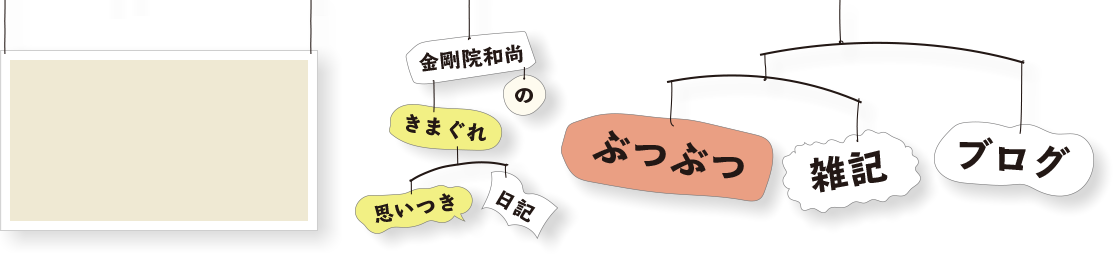

 500年の歴史を誇る
500年の歴史を誇る