
お釈迦様が亡くなったとされる日で、多くの寺で法要がおこなわれます。
2月15日ですが、旧暦にあわせて3月15日に行うところも少なくないようです。
涅槃とは、あらゆる煩悩から超越した境地のことで、サンスクリット語では
ニルヴァーナといいます。
悟りを開き、生老病死という苦しみの続く六道輪廻(生まれ変わり)からも解き放たれた
わけですから、お釈迦様が涅槃に入られたことは本来嘆き悲しむことではありません。
しかし、悟りにいたらない我々一般衆生にとっては、死という別れの瞬間はどうしても
悲しまざるを得ないもの。
そんな様子を描いたのが釈迦涅槃図で、涅槃に入られたお釈迦様のまわりで、高弟をはじめ、
動物から神霊にいたるまであらゆるものたちが泣き、打ちひしがれる姿が記されています。
またその姿を絵ではなく像であらわしたのが涅槃仏。わかりやすく寝仏ともいいますが、
お釈迦さまの涅槃の状態をできるだけ忠実にあらわすため、頭は北に、顔は西に向けて
安置されるのが通例となっています。
お釈迦さまはいつも頭を北にして寝ておられたそうで、涅槃のときもそうであったという
話に基づいています。有名な話ですが、これがご遺体を北枕にする風習のはじまりというわけです。
北枕というと縁起が悪い…と思いがちですが、ルーツを考えれば決してそんなこともないのですね。
世界でもっとも有名な涅槃仏は、タイの首都バンコクにある、全長46メートルという巨大涅槃仏。
ワット・ポーというお寺にあるもので、長いだけでなく高さも15メートルと優に東大寺の大仏さま
ほどあるといいますから、その巨大さが推し量れます。
さすが、仏教王国タイの面目躍如といったところ。
じつは日本にもこれに匹敵する巨大涅槃仏があります。
真言宗別格本山である福岡県の南蔵院にあるもので、その全長は41メートル、
ブロンズ製の涅槃仏としては世界最大だともいいます。
もちろん大きさイコール信仰の強さというわけではないですが、大きな仏像をつくろうとする
意志やプロセスは、必ずあつい信仰心に裏打ちされているもの。
これだけの巨大涅槃仏をつくり、拝もうとした先達を思うと、ぜひその心を受け継いで
いきたいという気持ちになります。
余談ですが、お釈迦さまはたいへん大きな人だったという伝説もあり、それによれば
身長はなんと5メートル近かったとのこと。
もちろん現実にそんなわけはありませんが、お釈迦さまの偉大さを庶民にもわかりやすく
説明しようと、考えた人がいたのかもしれません。
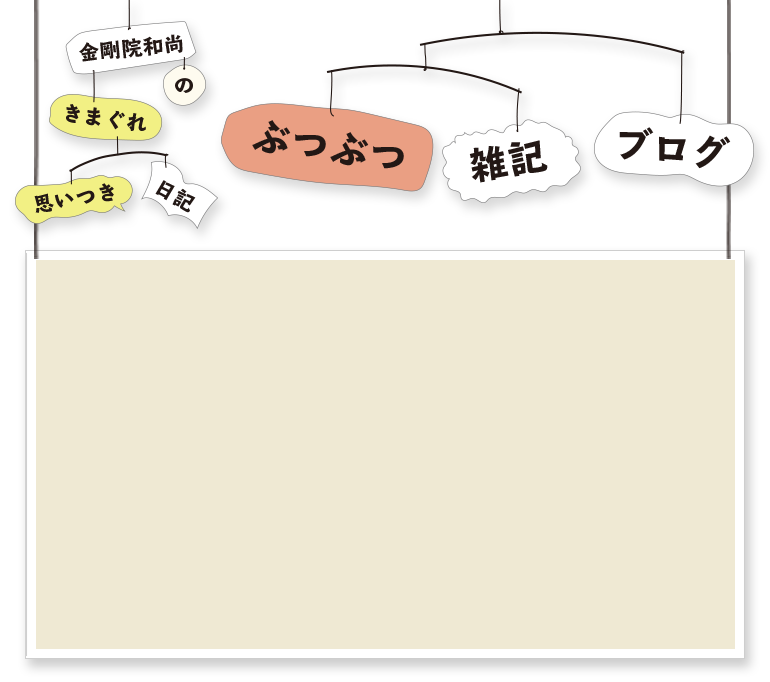
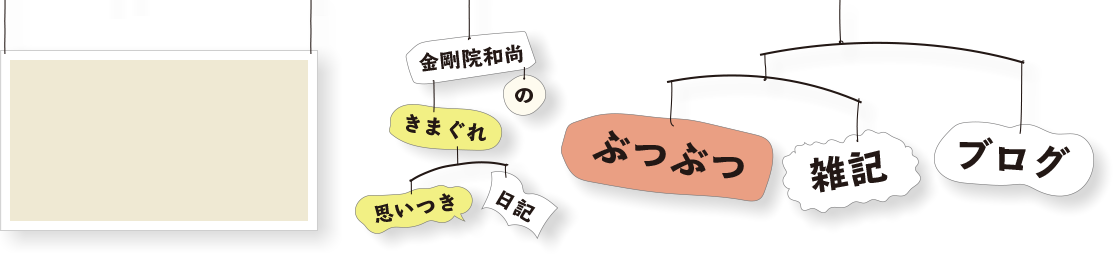
 500年の歴史を誇る
500年の歴史を誇る