5月ももう残りわずか。ずいぶん暑くなってきました。
とはいっても、4月5月は一年の中でもいちばん過ごしやすい時期です。
週末ともなると、あちこちで野外イベントが催されたり、フリーマーケットが開かれたりしています。
このフリーマーケット、誰でも自由に売り買いができるからFreeマーケットなんだと思われる
ことも多いようですが、これはよくある誤解で、フリーというのはflea、害虫のノミのことです。
もとはフランスの言葉で、ノミのついているようなボロ布やガラクタを売っている市場のことを
言ったのだそうで、日本語だとボロ市というのが一番近いでしょうか。
直訳の蚤の市というのもよく耳にします。
5月が終わって6月になると暦の上では夏のはじまりですが、日本ではその前に梅雨がやってきます。
仏教の発祥地インドには梅雨というものはありませんが、かわりに梅雨よりもさらに長い雨期の
季節があります。規模も梅雨の比ではなく、大雨によって川が氾濫することもしばしば。
現代でも自由に外出できなくなることがままあるようですが、古代インドの仏教教団は、雨期には
あえて外出を控え、お寺やあるいは洞窟などにこもって修行三昧の日々を送るというルールをつくっていました。
この修行のことを「安吾(あんご)」といいます。
雨期に行う修行なので「雨安居(うあんご)」、また雨期は夏にやってくるので「夏安居(げあんご)」
ともいいます。
安吾が雨期に行われたのは、外出が難しくなるからということもあったのですが、もうひとつ別の
意味もありました。
雨期は草木の成長の時期、そして虫や小動物も雨を避けてさかんに動き回る時期とされました。
そんな季節にむやみに外を歩き回ると、その大切な芽や小さな虫たちを踏み潰してしまったり、意図せずに
傷つけてしまう可能性が高くなる。だから屋内にこもり、無益な殺生を避けて修行に専念しよう、
ということになったのだそうです。
ちいさな虫の命も大切にする。命の価値は平等である。
そんな仏教の精神の本質をみるような気がいたします。
嫌がられるノミのような小虫でも愛でるのが、仏さまの教えだといえるのかもしれません。
ちなみにお坊さんの着ている袈裟(けさ)、いつの頃からかずいぶんと派手になっていますが、
本来は「糞掃衣(ふんぞうえ)」とも呼ばれ、それこそノミのたかるようなボロ布の切れ端を
縫い合わせて作るものとされていました。
古代インドのお坊さんが現代の蚤の市、フリーマーケットをのぞいたら、あまりの豪華さに
ひっくり返ってしまうかもしれませんね。
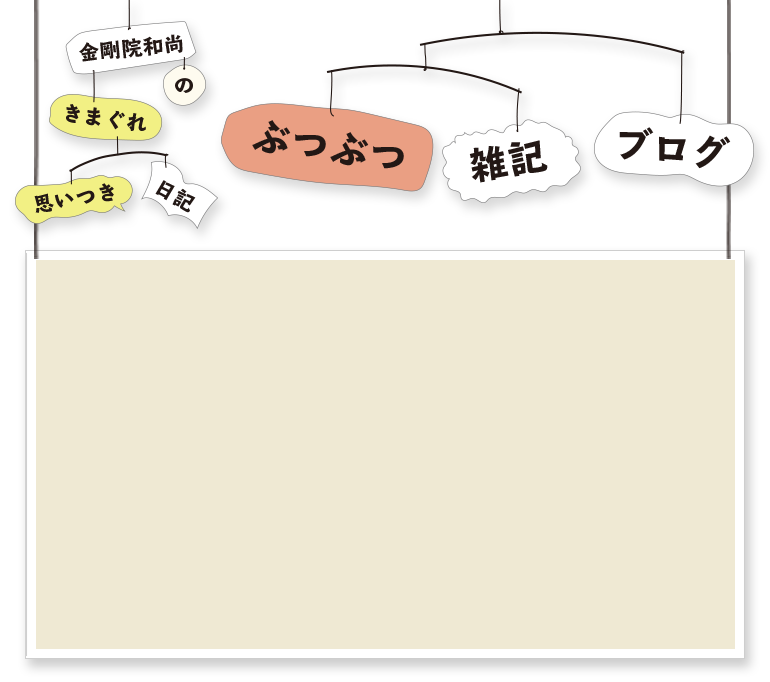
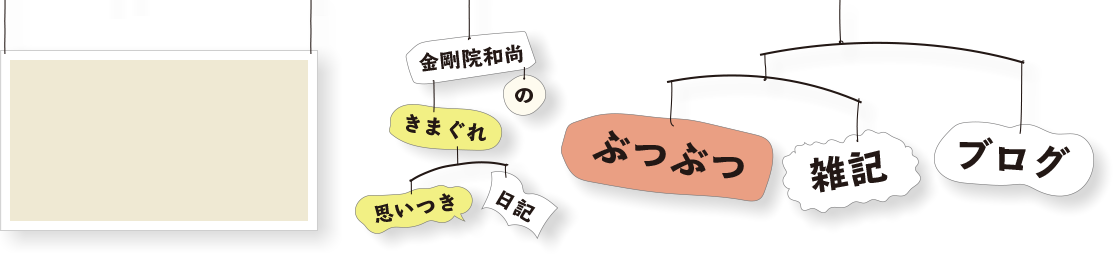

 500年の歴史を誇る
500年の歴史を誇る