
暑さ寒さも彼岸まで・・・なんて言われて
いましたが、今年は暖冬で関係ないと思って
いたら、寒の戻りというかお彼岸中は寒いみたい。
「毎年よ彼岸の入に寒いのは」とは、有名な
正岡子規の俳句です。母が何気なくつぶやいた
言葉がそのまま俳句になっているとか・・・。
最近は何でも機械で計測したりするけれど、人間の
持っている皮膚感覚や経験から感じることって
大切なことが多いのでしょう。
「知目行足」・・・確かに知識などで知ることは
大切だけれど、その教えが「わかる」ということは
「実践&感!」が必要なのかもしれませんね。
というわけで、お彼岸中には、ご先祖の「お墓参り」を
通して、いろいろなことを感じてみてくださいね
写真by古津昌典氏
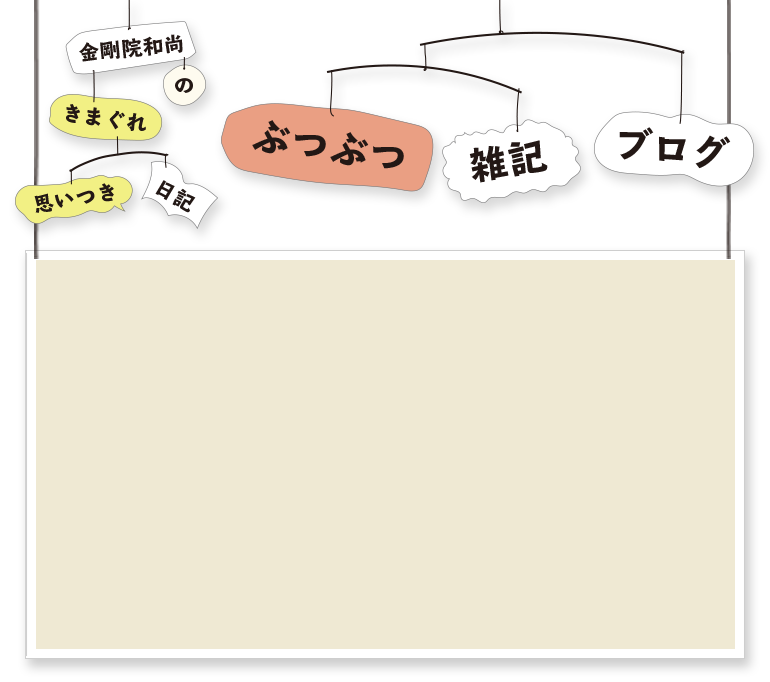
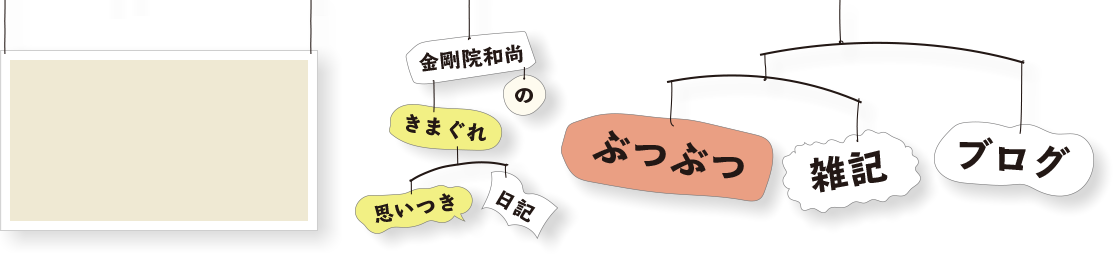
 500年の歴史を誇る
500年の歴史を誇る
寒かったです。。
今日は、両親ともに仕事だったので、一人でお墓参りに行ってきました。
海のすぐそばのお墓なので、我が家のお墓もご先祖様のお墓も、強風に吹かれて寒そうでした。
でも、どこのおうちもお花やお供え物があげられていて、寒くても明るい雰囲気でした![]()
もう少し暖かくなれば、いいですね。
本当ですね
我が家のお彼岸はちょっと変わっていて、親戚中のお墓を一日二日かけて回っていきます。おまいりのハシゴ状態です。というのはお墓も菩提寺も府外にあり京都の郊外に位置してるのでちょっとした旅行状態だからです。そして
高齢化、過疎化の影響で墓守も寂しくなった老いたご婦人(叔父さんたちはなぜかみな先立たれている・・生命力の性差なのか?)が多い。墓参りの後家庭訪問するととても喜んでくださる。その交流が楽しみでもある。「ああ今日もお元気だ・・とかちょっと調子が良くないのかな」とか寂しくても友だちに囲まれて幸せに生きておられるのを見ているとこちらも元気付けられるのです。それを義父や義母に報告すると安心してくれる・・(こちらも高齢でお墓参りが困難)
お彼岸などの節季はこのような家族のふれあいの場を与えてくれます。
御仏の教えは確かに経典やその解説にも難解なものが多く、実際に「師」について学ばなければ本当の身にならないものだそうです。
しかし思うのです。今の社会の状態や風潮にあり一庶民が皆がどれだけ真の「法」を説くご縁に会えるか・・と考えたとき、まだまだその門は狭く、それを求めて行脚する作業すらも困難でありましょう。
そしてもひとつ、家族の理解、も必要になってきます。
Osyouさんのおっしゃる事、私目も耳が痛いです。
「実践と感」・・
短い間ですが、生きてきた中にもっと早く、仏教の教えに親しんでいたらと思うのです。![]()
ゆがさま
なかなか大変なお彼岸ですね。お檀家さんでも
お墓参り&家庭訪問されている方は、たくさん
おられます。本当に「偉いな」と感心してしまいます。なかなかできることではありません。
先日、和尚の尊敬する大学の先生が、仏の学問は、
ウナギの串みたいなもので、焼くときにはとても
重要でなくてはならないけど、お客様に出す時には
串を抜いて出さなければいけないと・・・。
確かに・・・。
綺麗な器も必要だし、山椒の一味も妙にウナギが
美味しく感じられる・・・そうでないとウナギが美味しく食べられない。
教典を学び理解することは重要です。でも、仏の教えは、それだけではないことも確かです。
そして自分の回りには、いろいろな教えや気づきがあって、アンテナをたくさんのばしておきたいなぁと、いつも思っています。
だから??「Osyou」の大文字いいなぁ・・・。
なんて、思ってしまいました![]()
ゆあんさま
和尚も掃除がてら墓地を一回りすると
水で清められ、お花やお線香が供えて
あると温かい感じがしますね
でも、お参りされていない墓地を見ると、何だか
淋しそう・・・
うらめしい~~~~とは、
ここからくるのだ![]()
晴れやか
私もこの世に生を受け?年経ちましたが、ひと月のうちに 3回も お参りしたことは 初めてでしたが
なんと 清々しいこと・・
お天気に恵まれ あちらこちらで お久しぶりお元気でしたか? の声がきこえて なんか私まで、ほのぼのとして、今まで我が家のご先祖様に手を合わせるだけでしたのに まわりの仏様が気になる自分がおりました。 そんな年齢になったのですね
ひろこさま
ご先祖のお墓をお参りするときに、
「お世話になっているから」と両隣のお墓を
お参りする方もいるんですよ・・・。
もちろんご年配の方ですが、お連れのお孫さんも
マネをして手を合わせている姿をみると、
なんかほのぼのした感じになります![]()