おさいせん泥棒を捕まえた。
子供ではなく大人だ。
こういう人たちは、現行犯でも取ったとは絶対に言わない。
ただただ手を強く握りしめて寡黙になるか、あるいは怒りだすか
どちらかだ。
今日のタイプは後者の方で、いきなり怒り出した。
怒るという行為は、案外「真実」を指摘されたために
自己を防衛するための行為であることが多いように思う。
さてさて、本来のおさいせんの意味は、
仏さまと「結縁(けちえん)」つまり身近に
縁を結ぶことを現している。
良い「ご縁・(ごえん)」が結べるようにと「5円」を
差し上げたり、あるいは「遠い縁・(とうえん)」になるから
「10円」はダメだとか、仏教的には根拠のないことだが、
そう信じている方も多いようだ。
お財布にたまった1円玉を整理するかのように、1円玉を
おさいせにする方もいるが、くれぐれも「結縁がケチ縁」に
ならないようにね・・・。
そんなことはない!!プンプン!!と怒らないでね~。
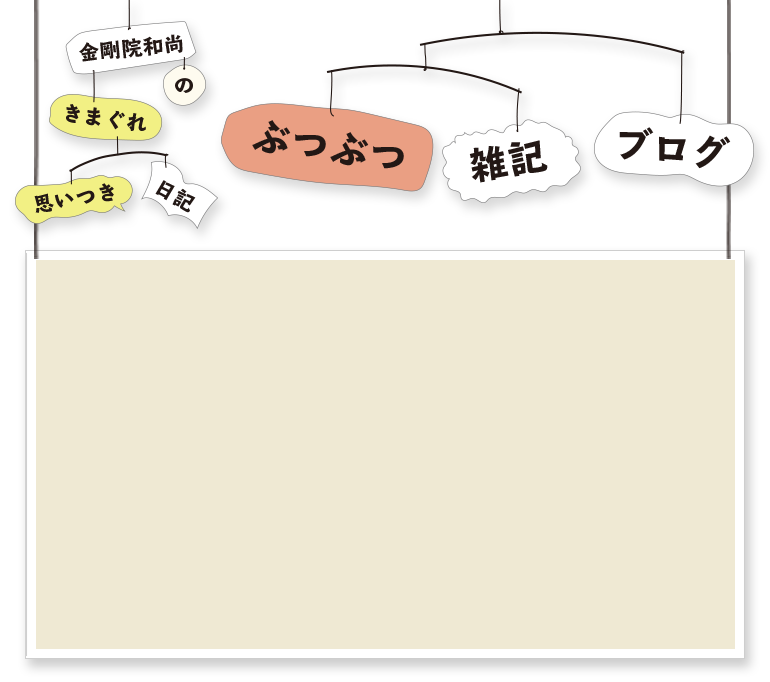
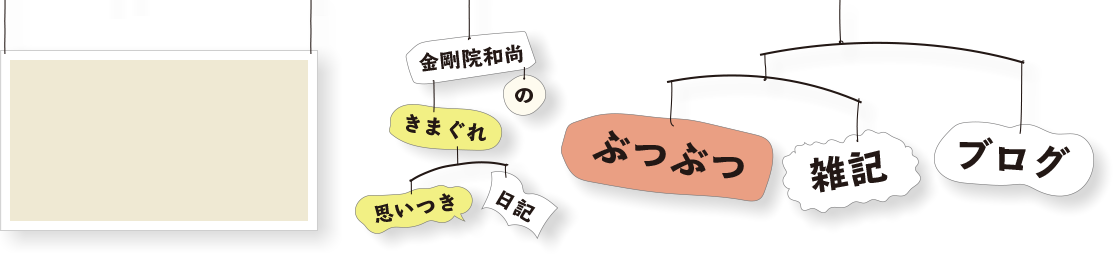
 500年の歴史を誇る
500年の歴史を誇る
お手柄!
先日のオレオレ詐欺に続き今度はお賽銭泥棒ですか。お寺っていろんなことがあるんですね。
その後その泥棒はどうされたのでしょうか?
和尚さん、お手柄でした。
突然ですが質問です。お賽銭っていつごろから始まったものなのですか?
ふと気になったので…。教えてください。
泥棒のその後?
悠々と歩いていきました。
近くに交番もあるのですが、お賽銭泥棒は日常茶飯事で、おまわりさんも気が入らないみたい。
ちなみにお賽銭は、もともとはお金ではなく、珍しい物や大切なものを供えました。
昔は洗米(せんまい)といってお米を洗ったものを使用しました。お米が大切な時代です。
お金が一般に流通しはじめると、お米より手軽
なお金が使われるようになりました。
9世紀頃には中国で仏様へお賽銭を供える風習があったといいます。
日本では、お金の流通が本格化したのが室町時
代頃と言われています。