
お彼岸の始まりはよくわかりませんが、『源氏物語』の
「行幸」(みゆき)の巻に「彼岸の初めにて いとよき
日なりけり」という表現があることから、平安時代から
行われていたようです。
彼岸が春秋に7日間と定められたには江戸時代の頃で
国民の祝日に関する法律の中には、「秋分の日」を
「先祖を敬い亡くなった人をしのぶ日」とされています。
この日が、お彼岸の真ん中の日、つまり「中日」(ちゅうにち)で
その前後3日間の1週間が、仏さまのことを、ご先祖のことを、
心から思いながら過ごす「宗教週間」にほかなりません。
ぜひ「善い行い」をつみ、それをお土産として心からの
お参りをしたいものですね
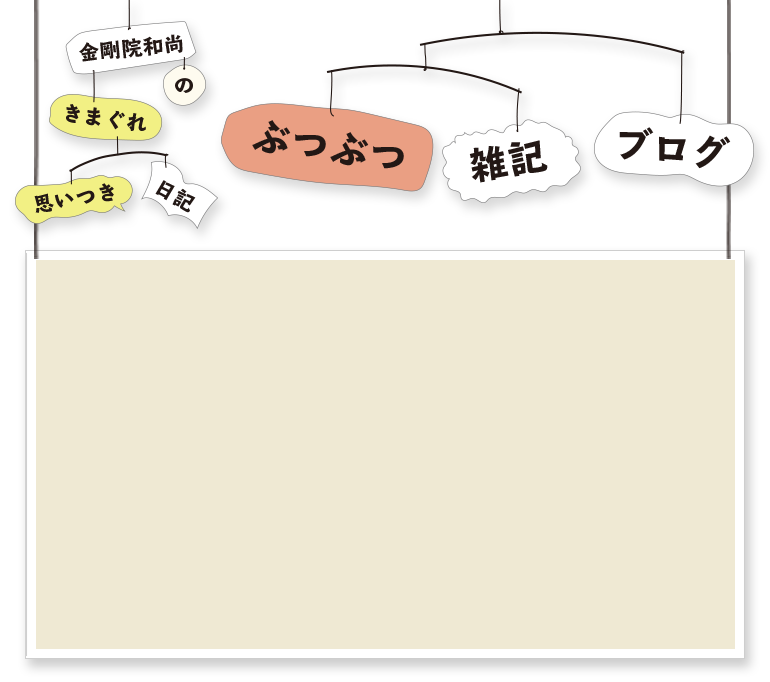
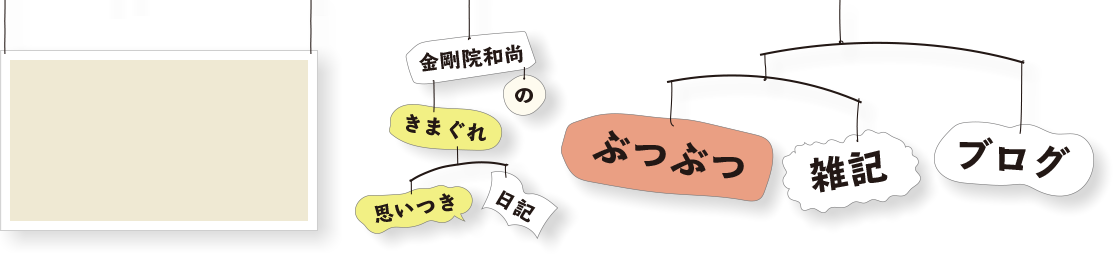
 500年の歴史を誇る
500年の歴史を誇る
お目にかかれず
今日のお彼岸は暑かったですね。こんなに暑いのは、初めてだ・・・と母がいっていました。冷たいお茶と美味しいお菓子頂きました。
太郎さま![]()
今日は書類の寺務整理で裏にこもって
いました。一時お参りラッシュの時には
お線香をつけていましたが、火鉢の暑さは
格別です