
仏教界では最もおめでたい日のひとつである4月8日の花祭り(4灌仏会)もつつがなく過ぎ、
この頃になると毎年桜も満開を迎えます。
4月は旧暦で「卯月」といいますが、なぜそう呼ぶのでしょうか?
春になって、生き物の新しい命が産まれる月「産み月」がなまったもの、十二支の4番目の卯をあてたもの、
など諸説ありますが、一番確からしいとされているのは、旧暦4月頃になると卯の花が咲くことから「卯の花月」、
これが縮められて卯月になったという説です。
卯の花といっても食べ物のおからのことではありません。
真っ白な小さな花をたくさん咲かせるウツギの花のことを卯の花というのです。
ウツギは丈夫な木なので植栽にもよく使われます。お寺の庭でもよく見かけますよね。
最近ではあまり耳慣れないかもしれませんが、かつて農業が盛んだった時代には、4月8日は花祭りとあわせて
「卯月八日」という行事もおこなわれていました。
竹竿に卯の花やツツジなど季節の花を飾り、庭に立てておくといった風習があったのですが、これは山の神さまを里に迎えて、
一年の豊作を祈る意味があったと考えられています。
仏教の伝来前から行われていた古い習俗で、花を飾るしきたりは花祭りにも影響を与えたのではないかとも言われています。
仏教の祭日が、さらに古い民間信仰とも結びついているという例は意外におおくみられるものです。
大昔から大切に大切に残されてきた行事。これからも守っていきたいですね…。
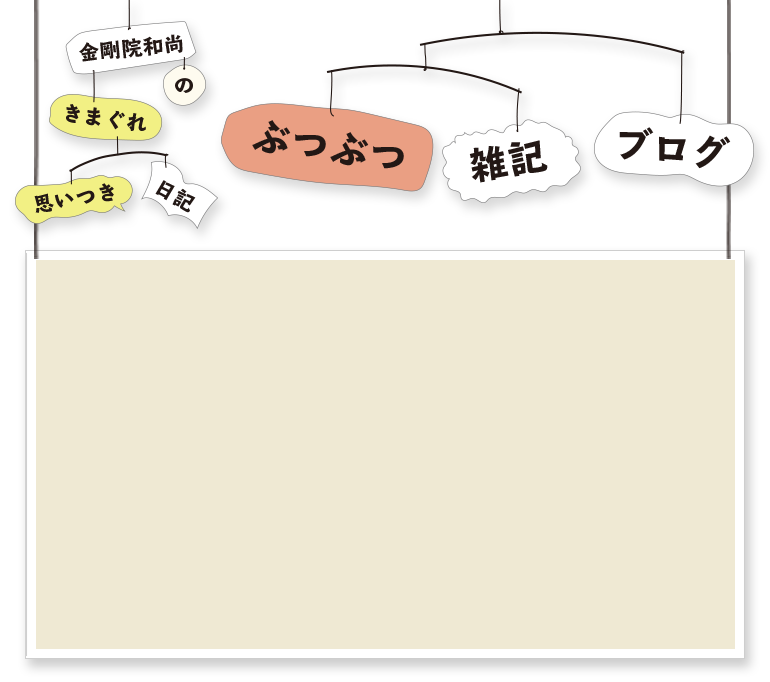
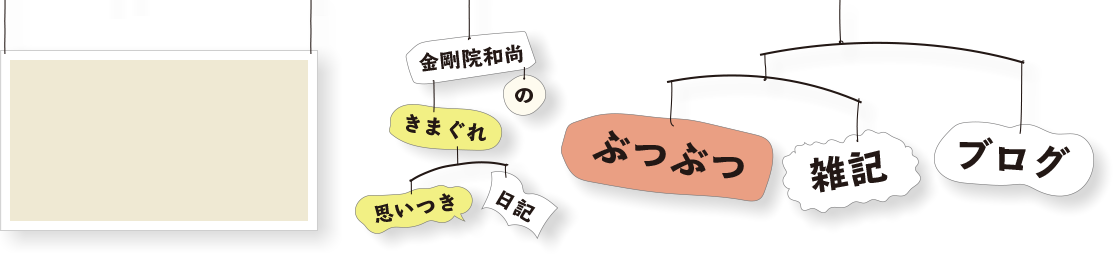
 500年の歴史を誇る
500年の歴史を誇る