
和尚の寺では、お正月三が日にお出しするお茶は
「大福茶」(おおぶくちゃ)というお茶です。
いまから1000年ほど前に京の都では疫病が蔓延し、
六波羅蜜寺の空也上人が、自ら十一面観音を刻み、その
尊像にお供えしたお茶を病気で苦しんでいる人たちに
飲ませると、あら~~不思議と病気が治ったとか・・・。
以来、幸せをもたらす意味から「大福」の文字が当てられて
縁起のよいお茶として伝えられています。
大福茶の中身は、梅干や昆布、玄米、黒豆、白豆、金粉など
お茶屋さんによって、さまざまです。
「良薬は口に苦し」と言いますが、昔の大福茶は不味くて
飲めませんでしたが、最近はここに緑茶や抹茶が入っていて
普通に美味しく頂けますの、ご接待しています。
そういえば、先代の住職は、朝起きると梅干しを食べながら
お茶を飲んで、それから動きだしていました。
旅館に泊まると床上げの時にお茶と梅干し、トッピングに砂糖を
持ってきたものですが、いまはあまり見かけませんね・・・。
そんな先人の知恵が、実は自然な健康法だったのかもしれませんね。
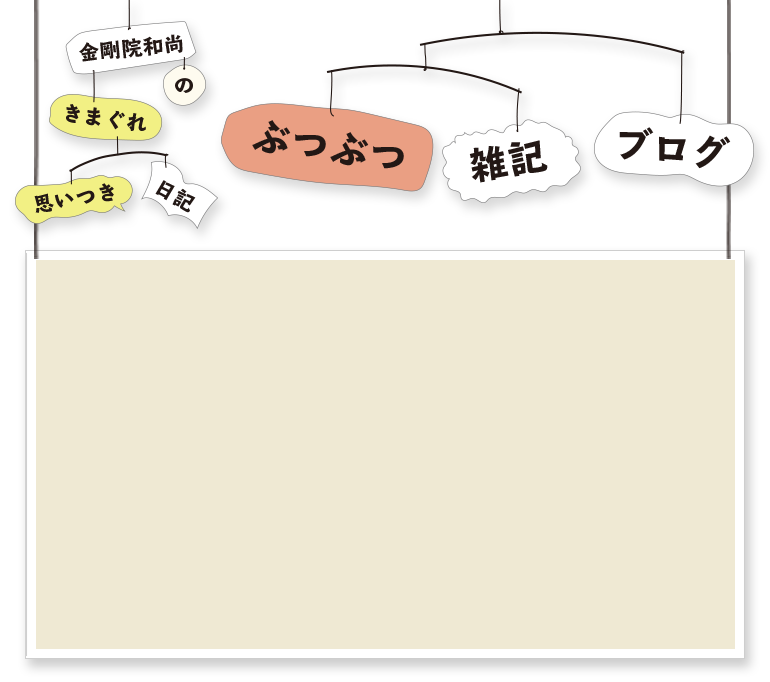
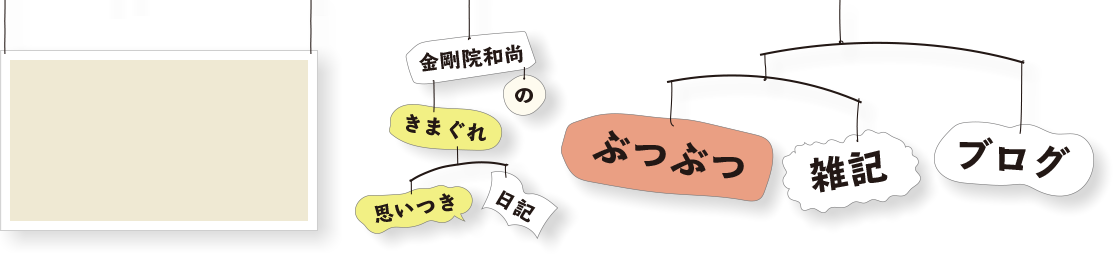
 500年の歴史を誇る
500年の歴史を誇る
あけまして![]()
あけましておめでとうございます
大福茶かぁ。![]()
今度、お茶屋さんに行ったら探してみます。
飲みたくなりました
「縁起がよい」という言葉にも、ついつい惹かれてしまいます。
お茶と梅干も、いつもおばあちゃんのおうちに
行くと、セットで用意されていて。
一緒に手作りのお漬物があったなぁ・・と
ふと思い出しました。
雪と共に、新年を迎えて無事にお札も頂いて
今年もガンバルゾ~
と思い、中学校の「厄払い同窓会」に出席しました。
お知らせがきた時は、行くかどうか迷いましたが![]()
思い切って行ってよかったです
お坊さんや神主さんがきて、厄払いをして頂いた訳ではありませんが、恩師の方々や音信不通になっていた同級生と再会できました![]()
たくさん思い出話をして、たくさん笑って![]()
とっても楽しかったです
良い1年になりそうです![]()
ゆあんさま
おめでとうございます。
「厄払い同窓会」て、凄いですね。![]()
皆さん厄年?だから大いに笑って厄が逃げていった
かもしれませんね
夢の多い年になると良いですね~~![]()