
宗派で発行している「光明」という施本の取材で
管長猊下のインタビューに伺いました。
来年の新春号取材なので、写真撮影の関係もあり、
猊下には、お暑い中にも関わらず冬物での取材で、
ご迷惑をかけてしまいました。
我々のような者が、管長猊下の間近でお話を伺える
ということは、この役職ならではの特権でもあります。
そんなお話の中に、江戸時代には猊下のお寺からご本山の
長谷寺まで勉強に向かわれた方がいたとか・・・。
その当時、真言宗豊山派のご本山は「学山」と呼ばれていて
学びの場所として、2000名近い僧侶が、本山にいたそうです。
長谷寺の記録の中にも、一斉にとろろ汁を吸うと、門前町に
ゴォ~~という大きな音がしたとか・・・。
当時のお坊さんにとって、徒歩しか交通の便がなく3週間以上も
かけて、ご本山まで行かれるということは、まさに命がけでもあり、
強い求法の志があってのこと・・・。
新幹線で気がつけば、到着という現代と比べれば、何とも
頭の下がる思いです。
その後、ご本山も廃仏毀釈と幕藩体制の崩壊などで、一時期は
2名ほどしかお坊さんがいなかったとか・・・。
栄枯盛衰とはいえ、行政の方向性と財政を支える基盤は、寺院運営に
大きなダメージを与えたようです。
平成の時にあって、一寺院を維持、管理していくには、外からでは、
目に見えない苦労があります。
大きなお寺に就職して、お給料をもらっているお坊さんもいますし、
お寺を持たないで派遣お坊さんとして、1日に何件ものお葬式を司る
お坊さんもいます。
伽藍と伝統を抱える和尚にとっては、10年後のお寺をどのように
デザインしていくのか・・・?
案外と伝統を守り続けて、何も変わっていないということが
大切なことなのかもしれませんね!!
どこかに大きな智慧がないかと、キョロキョロとアンテナを
伸ばしている毎日です。
あっ 写真は、本山長谷寺に入ると一番最初に目に
写真は、本山長谷寺に入ると一番最初に目に
とまる399段の登廊・・・。
今は亡き松本清張が、「美しすぎる、あまりにも美しい・・・」
絶句した場所でもあります。
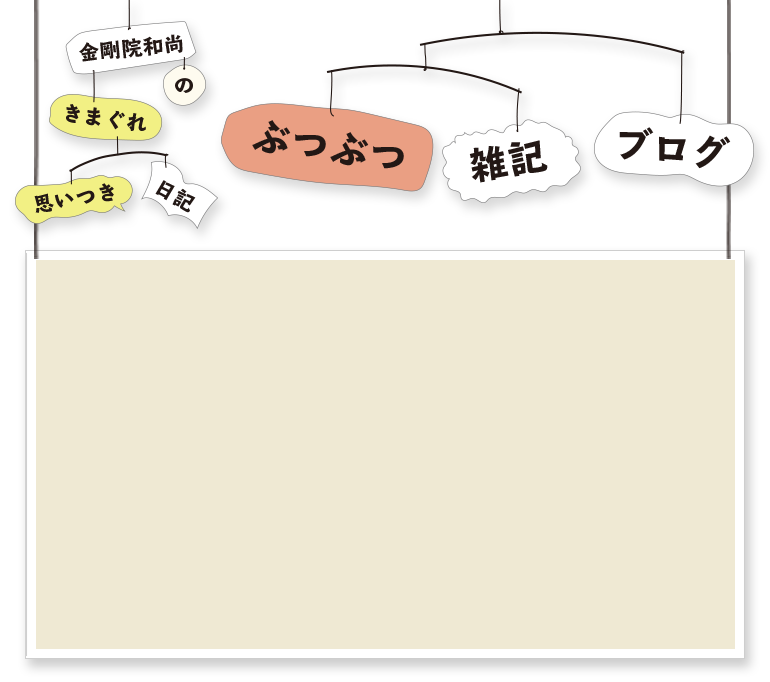
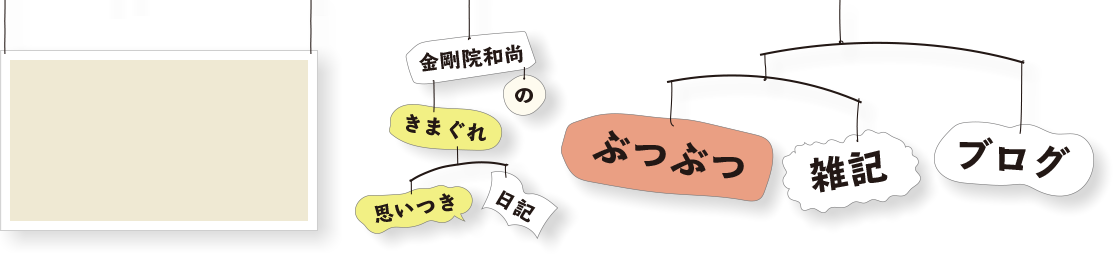
 500年の歴史を誇る
500年の歴史を誇る
果てしなき
修行の道を象徴するかのような、見事な階段でございます。(-人-)
諸行無常
の世の中です。どのよいに変わるのかどうなるのでしょうか?変わらないことも変わることと言うこともあるようです。本日佐渡島に行きました。北条時宗に1271年佐渡島に配流された日蓮聖人にまつわるお寺をお参りして来ました。合掌。
4つのC
背骨でございます。
こんな時代だからこそ、お寺の重要性はだんだん高まっていくような気がします。
例えば、高齢化。
単に寿命が延びるというのではなく、「決して良くなることのない病気と向き合って生きる」人も増えてきているはずです。現代の医学や医療システムでは、知覚神経に感じる痛みを取り除くことはできても、病気を抱えた人の心の苦しみや、死と向かい合う恐怖を取り除くことはできません。こういうことこそ、お坊さんの出番なのではないのでしょうか。「仏教ホスピス」と大上段に構えるのではなく、地域のコミュニティの中で出番はあると思います。「ハケンのお坊さん」では、コミュニティに溶け込んで活動することはできないのですから…。
care(看取り、介護)
cure(癒やし)
culture(文化)
community(コミュニティ)
の「4つのC」がキーワードなのかも知れませんね。
個人的にはここのお寺に一度行ってみたいです。
http://www.senkouji.net/
ナベさま
ご本山の階段は、誰でもが登りやすいように
最初は段差がほとんどありません。
しかし3番目の登廊階段になると、見上げる
ような厳し段差となります。
観音様にお目にかかるには、それなりの清浄さが
必要なのでしょうね。
フードアナリスト食人さま
変わらなければいけないこと、変わっては
いけないこと・・・。
その選択があるように思います。今の世の中を
見ていると、気がつくと足下が何もなくなって
いた・・・なんてことがありそうな気もします。
背骨さま
全興寺さんは、いろいろと見所がありますね。
大阪・平野散策もおもしろいかもしれません。
地獄堂は結構コワ~~いです。
そうなんですよね。
ハードよりもソフト。
ソフトからハードを考えていかないと・・・
和尚的には4Cに「祈り」も入れたいです。
これからもお願いします!!