
明日のお施餓鬼法要の準備で、朝5時から活動
開始です。建物の中をあっちへ行ったり、こっちへ
来たり・・・。
万歩計を借りてどのくらい歩いているのかみたら
お昼までに12,000歩です。
大勢の檀家さんとお坊さんを呼んで、皆さんと共に
行う「ご功徳」法要です。
「願わくは、この功徳をもって、あまねく一切におよぼし・・・」
と唱えられ、本当に素晴らしいなあといつも思います。
ご婦人方は、これからお弁当の下準備です。
にんじん、シイタケ、がんも、こんにゃく、たくあん、
昆布、赤飯などと、30年間以上も変わらないメニューです。
飽食の時代にあって、こんなシンプルさが新鮮なのかも
しれませんね。
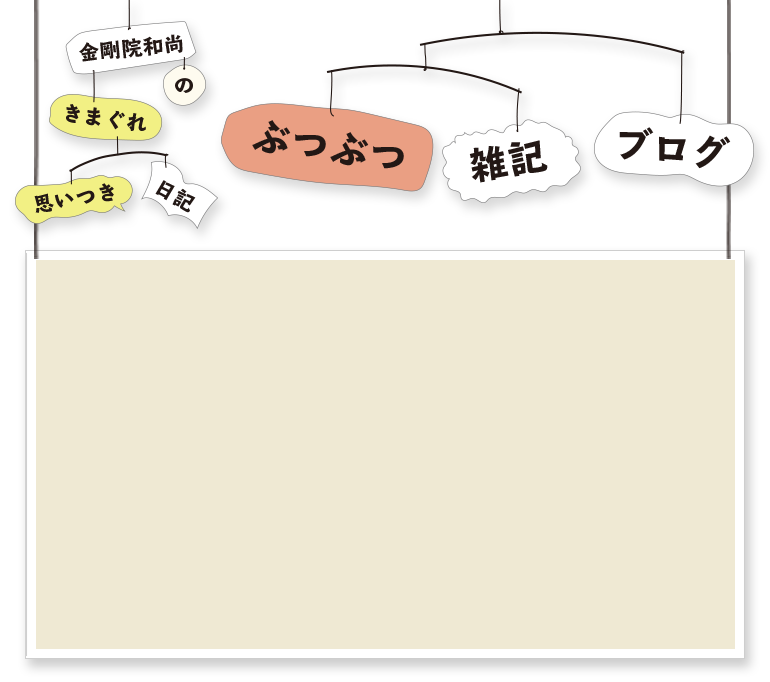
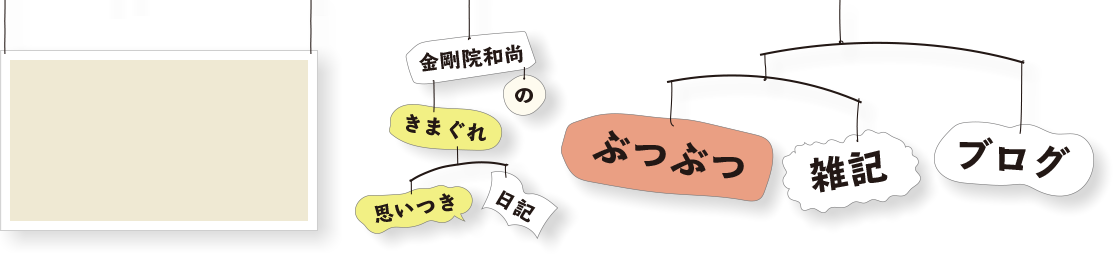
 500年の歴史を誇る
500年の歴史を誇る
Unknown
お疲れ様でございました。お寺さまの年中行事(この表現でよいのでしょうか?)は、どれくらいあるのですか?和尚さまは、お休みはないのでしょうか?
Unknown
大勢のお坊さん、檀家さんでした。和尚と、女性の住職の法話を聞くことができてよかったです。
いつもは、あまり口にしない、お赤飯のお弁当も、大変美味しくいただきました。
お疲れさまでした![]()
今日は暑かったので大変でしたね。
女性のお坊様のお話は、素直な話で心の中に
自然と入ってきました。
ご詠歌も素敵でした。
私もお坊さんになろうかしら・・・?なんて
考えてしまいました
Unknown
恐れ入りますが、法要の際に撒かれる絵の書かれた紙について教えていただけないでしょうか。
玉虫さま
ありがとうございます。
師僧から、法要の行事あとは、しばらくの間
その余韻を、そのままにしておかなければ
ならないと教えられたことがありますが、そんな
ことをしていると来週は「お盆」なので、
後片付けも本日で終了です。
最近は、毎週○曜日が定休日というお寺さんも
あるみたいで、うらやましいやら変な感じやら・・・。
田楽さま
皆さん男の方だと思っていたようでビックリ
したみたいです。お寺も女性の方が多くなって
きました。
今年のお弁当は、ちょっとインパクトに欠け
ましたね。
アンさま![]()
![]()
女性の方のご詠歌は、やさしい感じがしますね。
「お坊さんになるの?」
お待ちしています~~
お答え
これは散華(さんげ)と言います。
仏さまにお花を供えるので「供花」。
お花を散ずるので「散華」といいます。
昔は本当の花の花弁をまいていましたが、
いつの頃からか、花弁の形をした紙に季節の
花の絵を描いて撒いたのです。
また、花の代わりに仏さまや極楽浄土を模した
ような絵を書くようになり、それを撒くことによって、その場所が仏の世界となるような思いも
あったようです。
これを御守りのように持たれている方や、ある
地方ではタンスの中に入れておくと着物には
不自由しないとか・・・。
信ずれば、何とか??ですね。