
仏像などを安置する箱のことを厨子(ずし)といいます。
大切な箱なので金属などを加工して装飾を施します。
金属を制作するには、まず彫金(ちょうきん)といって
鏨や鋸、ヤスリ等を用いて、意図する模様・図案などを
整えます。それは職人さんの手先の感覚だけで行うのです。
次に鍛金(たんきん)という金槌や特殊な工具で金属を
たたいて加工していきます。
ノートパソコンぐらいの平面に加工された飾り金物ですが
実に精巧に出来ています。
小さいながら立体的な重厚感があり、金属の端の部分も
角の部分が、しっかりと面がとられて、それが均一に
流れるようにできています。
いま写真のような同じものを作れば100万円は、かかって
しまうかもしれませんし、ひょっとしたらその技術すら
ないかも・・・。
江戸時代のころの飾り金物なので、職人さんの技術や
「念をこめる」気持ちが違っているのかもしれませんね。
「良いものを作れ」そんな職人さんを育てる太っ腹の
旦那さんも多かったのも事実です。
すばらしい日本の伝統技術も、これから先細り
生活様式も西洋化してきてしまいましたが、もっと
日本の「和」に頑張ってもらいたいです
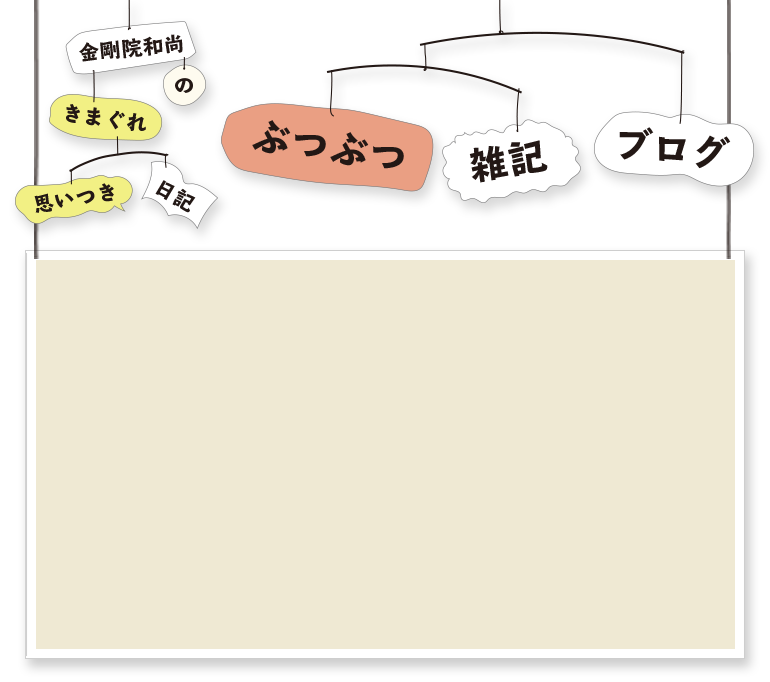
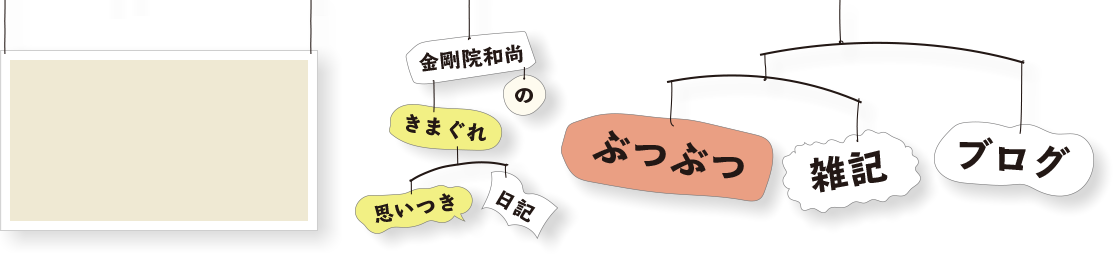
 500年の歴史を誇る
500年の歴史を誇る
そうですね、
そうですね、日本の技術はテクノロージだけが優先して
進んでいったでしょ、何か政治、経済も何処か違う方に
行ってしまい、もう庶民の生活なんて何処にも無いですね、
やはり宗教のような哲学が無いから何をやっても、市民は良く成らないよね、格差社会になったし、これでは夢や希望は無くなってしまうね、
不満ばかり言ってても仕方無いから、厨子のようなしっかりした目に見えるような形で競って頂きたいですね、
日本の古来からの生活様式もまた見直さないとね、
時間が過ぎても感動する物はやはり気持ちがこもって
居るんですね、人のが創る物で人を感じない物て
何処か寒い感じですよね。。
花粉症・・
今日、友達のおうちで建てた新築マンションの見学会に行ってきました。
とっても素敵な造りに、明るいお部屋にフローリング。
素敵でしたが、お部屋に入った途端、密閉されたせいか くしゃみが止まらなくて・・![]()
我が家は、純和風のおうちで、ほぼ家中畳です。![]()
父の実家も、昔ながらの純和風の家。
和風の家、畳の部屋では平気なのに、マンションや一人暮らしのアパートでは、密閉されすぎて反応するようです
大人になって、落ち着くのは昔ながらの食べ物や、昔ながらの伝統。
惹かれるのは、和の美しさ。
お花を始めて、やっと1年が経ちましたが、続けるうちに他にも習ってみたい事が増えました。
余裕ができたら、少しずつ身に付けていけたなら・・と思います。
やっぱり、昔からずっと伝わっている事は、温かくて・奥深さもあって、素晴らしいので![]()
後々にも伝えていって欲しいですね
すばらしいですね
私は昔に彫金のアクセサリーを作っていました。この飾りものが、どんなに骨の折れる仕事か想像できます。いまはプレスで簡単にできてしまいますが、一打一魂のオモイはなにものにもかないませんネ。
武雄さま
「心の時代」が大切と思いながらも、まだまだ
バブルを夢見ているようです。
うまくバランスがとれる仕組みが良いのですが・・・。
ゆあんさま
いつもお花の向こうに立派な床の間が・・・。
和室というか日本建築の木造はすばらしいですね。
でも和尚の寺は、防火地域で木造が建たない
区域なんです。
建て替えると「鉄筋山キンキラ寺」になって
しまいそう。
花粉症・・・お大事に!今はマスクをしていても
怪しい人に見られないから安心です。
さちさま
彫金ですか。細かい作業は器用でないと
できないですね。
どんな世界も「極めた」ものは、感動して
しまいます。
床の間は。。![]()
![]()
実は、床の間はお花の先生のお宅です
我が家の床の間は、現在お仏壇スペース。
なので、その近くにお花をたくさん飾っています
木造の建物には、温かみがありますよね。![]()
時代を感じる建物は、びっくりする程に繊細な彫刻や、しかけがあったり。先人の知恵はすばらしいですね
今日は、お寺のご近所の方のパッチワークの素晴らしい作品を目にしました。![]()
心をこめて長年作ってこられた作品。一目一目の全てに心がこもっていて、心底感動しました
でも、いつか将来に「鉄筋山キンキラ寺」が出現しちゃうのでしょうね・・何だか寂しいです![]()
ゆあんさま![]()
そうだったんですか
和尚も昨日パッチワーク見てきましたよ。![]()
檀家さんが個展を開かれたので・・・。
畳3枚ほどの大きな作品は見事でした。
素人でも感動できる作品て、多分その人の
魂がこもっているからなんでしょうね