
今日で阪神・淡路大震災から15年になります。
和尚がボランティアに出掛けたのが、ついこの前のような
気がします。
人の命のはかなさを、目の当たりにして愕然とした記憶が
いまも残っています。
お寺が崩壊した姿は、言葉に言い尽くせない衝撃で、
その傾いた本堂で避難住民と暮らし、境内のドラム缶で
作られた仮設風呂で、多くの住民が利用されていた記憶も
心に残る光景です。
震災は、ボランティアや地域のコミュニティーの大切さに
ついて、そしてお寺と地域との関係について、改めて考える
きっかけになりました。
いま考えてみると、各地で「地域に開かれたお寺」への挑戦が
始まったのは、阪神・淡路大震災のころからではないでしょうか。
最近では、本堂や境内を整備する時に、地域の防災拠点としても
使えるように設計を工夫する例もみられます。
和尚の寺のことを考えてみると、金剛院が「赤門寺」と呼ばれ
るようになったのは、江戸時代に大火で焼け出され、避難してきた
人を数多く受け入れました。
その功績が幕府に認められて、縁戚にしか許されていなかった
朱塗りの山門を許されました。
あと10年ほどで、お寺ができてから500年を迎えようとして
います。その時を目指して本堂などの建物の建築を考えています。
地域とともに金剛院の伝統、その良さを、これからのお寺づくりに、
どのように生かしていくべきなのか?
阪神・淡路大震災から15年が経った今日、あらためて考えています。
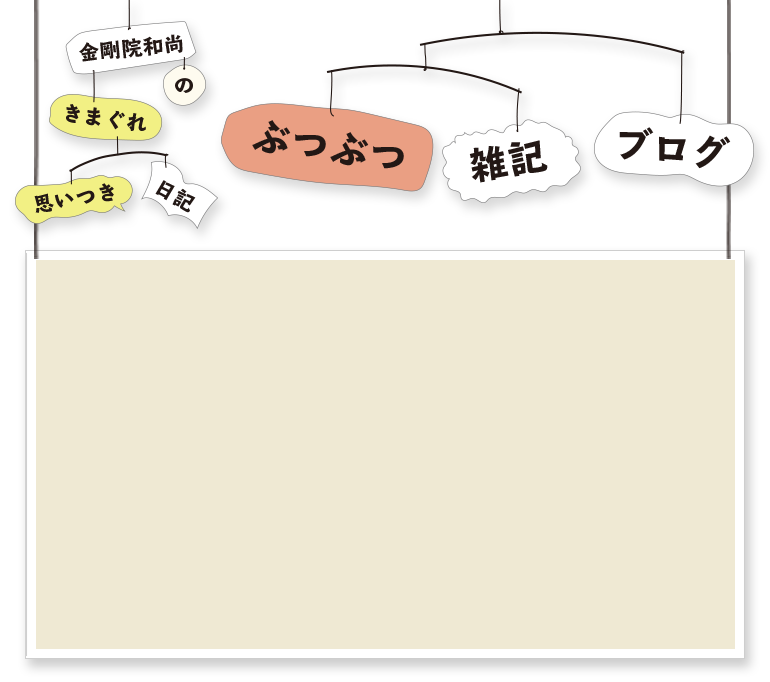
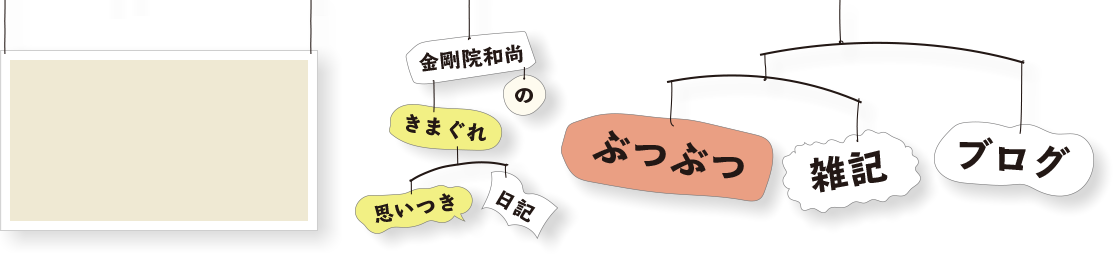
 500年の歴史を誇る
500年の歴史を誇る
お尋ね
和尚様
いつもブログを楽しみにしています。
神戸の震災から、15年ですか、、、。
私は大学で東京に出てきていて、震災のニュースを聞き、大阪の実家に電話したら、電話が繋がらなくて、焦った覚えがあります。
阪急線の駅近辺の崩壊の光景は、衝撃でした。
さて、またまたお尋ねしたいことがあります。
私は芝居をしているのですが、お世話になっている衣装さん(着付けなどをしてくださる職人さん)で、カミサマという方がいらっしゃいます。
カミさまのように着付けが素晴らしいということと、
実際、おうちが神道(富士山の山岳信仰だそう)で、衣装の仕事がない時は、神主さんなんです。
で、その方から、節分の大祭と、新年会のお誘いを
受けました。
私は、12月に母がなくなり、喪中です。
いつも1日と15日に行っている氏神様へも一年間、
お参りはしないつもりで鳥居はくぐらない様に過ごしています。
しかし、そのカミサマは、「実際は喪中でも、舞台の初日には神主さんがきてお祓いもするし、ケースバイケースでいいんだよ。」と言って、私が喪中なのもご存じの上で誘ってくださっています。
実際、その大祭と新年会は、女優さんたちが着飾って集まって華やかで、、、カミサマの生きがいなんです。
しかし、父にその話をすると、喪中なのに神社に行くなんて、けしからん!!ということになり、、、。
父の言い分が正しいのはもっともなのですが、私は仕事上のつながりもあるので、これはいきたいなあ、と思うのですが、、、迷ってしまいます。
和尚様は、どう思われますか?
カヤさま
カミサマが、そのようにおっしゃるなら、それも可かもしれません。
しかし新年会に、こられるたくさんの方もいて、
しきたりの大変な世界でもあるのでしょうから、
その方々が嫌がることもあるかもしれません。
スピード時代なので半年くらいなら、それも良い
かもしれませんが、12月の1月?で期間も短いので、私だったらお断りします。
なにか、その方が「形が良い」ように思いますし、
そういう「礼」を守れる方というカヤさまの
印象も、逆に好感を待たれるような気がします。
ありがとうございます
和尚様
お返事、ありがとうございます。
今回は、そのカミサマの会は、欠席させていただこうと思います。
和尚様のおっしゃる通りですね。
それに、母のために、たくさんのかたが思いを
よせてくださっている、そのお心も大切にしていかなくてはならないと思いました。
和尚様のおかげで、またひとつ、勉強を
させていただきました。
本当にありがとうございます。