
早いものでもうすぐ節分。
金剛院では、地域の振興や子どもたちにも豆を撒いてもらいたいので
立春前の日曜日行っています(今年は終了)
豆まきをする「年男、年女」を地域から募集しています。
年男、年女というと、今年ならば酉年生まれの方のこと。
その年の干支に生まれた、12歳、24歳、36歳・・・が年男、年女
ということになりますが、実はもともとの「年男」の意味は、ずいぶん
違ったものでした。
いまでも辞書には載っていますが、
本来の年男とは、年末年始の行事を司る男性を指すことばでした。
正月に神仏様をお迎えするためにしめ縄を新しくしたり、
新年最初に供える「若水」を汲んだりという、一年のスタートを
飾る大切な行事の数々は、歴史上ながく一家の大黒柱、家長がおこなう
大切な勤めとされていました。
田舎にいくと現在でも、年末にその年の秋に刈り取った稲わらで、
新しいしめ縄をつくるのはお父さん(あるいはおじいさん)の役目、
という習慣が残っているところがあります。
年明けにまつわる行事を司る男だから「年男」。
そしてそれは多くの場合家長の役目だったので、年男といえば家長を
指すことがほとんどでした。
それがいつの頃からか、お父さん以外の家族や、大きな家では使用人が
年男の仕事をつとめることも多くなっていきました。
だんだんと「年男」の該当者が多くなっていきます。
そして、さらにいつの頃からか、節分の豆まきをするのも「年男」
ということになり、さらにさらに、女性にもその役目を担ってもらおうと
「年女」ということばが使われるようになっていったのです。
その年の干支生まれの人を「年男、年女」と呼ぶようになったのは、
歴史的には比較的新しいことだったんですね。
豆まきには、豆をまく本人の厄を払うという意味もあるので、もし機会が
あれば、ぜひご近所のお寺の豆まきに参加してみてください。
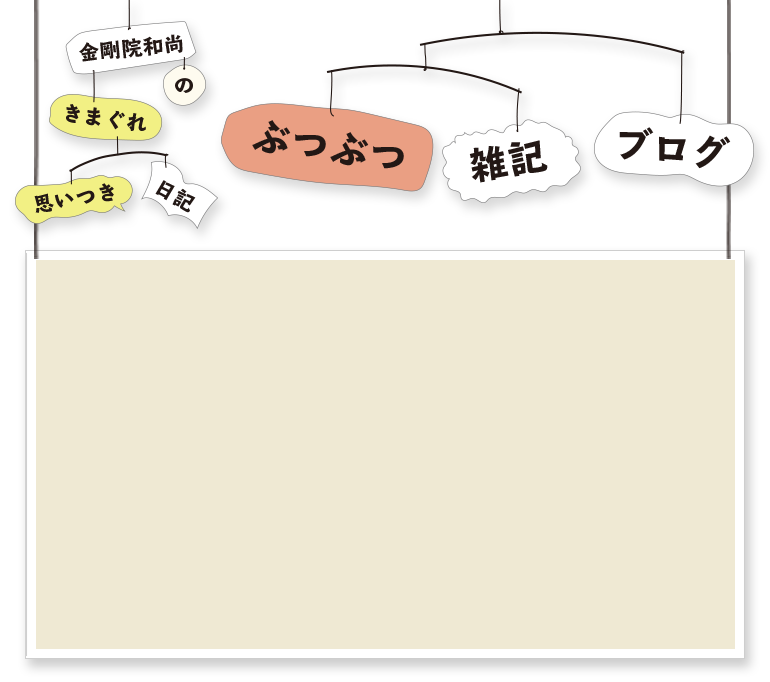
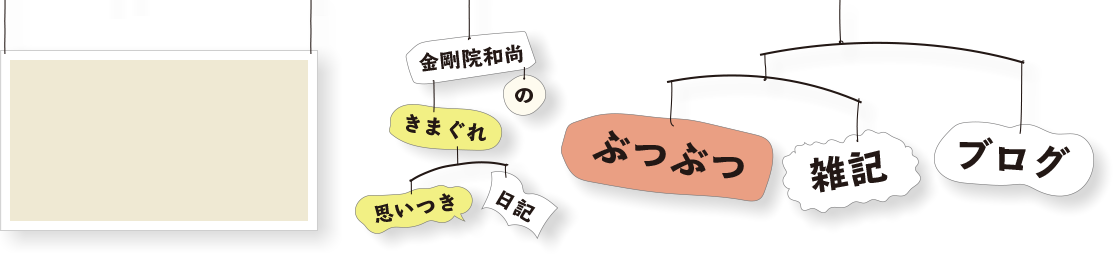
 500年の歴史を誇る
500年の歴史を誇る